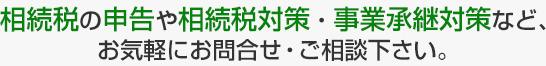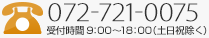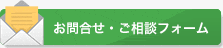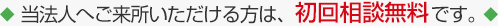2024年11月1日に施行されたフリーランス法により、発注事業者は、業務委託時に、フリーランスとの取引内容を明確にし、書面または電子的記録(メール・PDF等)で契約内容を交付する義務があります。
口約束や不明確な契約条件によるトラブルを防ぐことが目的です。
フリーランス法とは
フリーランス法は、フリーランスとして働く個人を保護し、適正な取引環境を整備するために制定された法律です。
フリーランスと発注業事業者との取引において、以下のような点を改善・保護することを目的としています。
適正な取引の確保
・曖昧な契約や不当な取引条件の是正
・書面または電磁的記録による契約内容の明確化
報酬の適正化
・報酬の支払遅延防止(原則60日以内の支払い義務)
・報酬減額・不当な値引きの禁止
ハラスメント防止
・フリーランスに対するパワハラ・セクハラの防止義務
・苦情処理体制の整備
【発注事業者とフリーランスの定義】
■発注事業者
業務委託事業者・・・・従業員なしの個人事業者・一人社長
特定業務委託事業者・・従業員又は役員がいる個人事業者・法人
■フリーランス
特定受託事業者・・・・従業員なしの個人事業者・一人社長
フリーランス法における義務と禁止行為
フリーランス法では、フリーランスと発注事業者の取引を公正にし、フリーランスが働きやすい環境を整備するために、以下のような義務と禁止行為が定められています。
【義務】
■取引条件の明示義務
発注事業者は、フリーランスとの取引内容を明確にし、書面または電子的記録(メール・PDF等)で契約内容を交付しなければなりません。
■報酬の支払い義務(60日以内の支払い)
フリーランスに対する報酬は、業務の完了日から原則60日以内に支払わなければなりません。
■ハラスメント防止義務
発注事業者は、フリーランスに対するハラスメントを防止する措置を講じる必要があり、相談窓口の設置などの具体策が求められます。
【禁止行為】
■報酬の減額
不当に報酬を減額することは禁止されています。
■不当な取引の禁止
フリーランスの立場を不当に弱めるような行為は禁止されています。
例:一方的な契約変更・業務追加の強要、契約解除時の一方的な不利益など
【その他(違反時の措置)】
発注事業者が上記の義務・禁止行為に違反した場合、公正取引委員会・厚生労働省などが調査を行い、指導・勧告・公表・命令を行う場合があります。
取引条件の明示
フリーランス法では、発注事業者がフリーランスとの取引内容(給付の内容・報酬額・支払期日など)を明確にし、書面または電子記録で契約内容を交付することを義務付けています。
口約束や不明確な契約条件によるトラブルを防ぐことが目的です。
契約内容の交付は、以下の方法で行うことが認められています。
・書面
・電子メール
・SNSのメッセージ
・チャットツール(LINEやSlackなど)
口頭のみでの契約はNGで、必ず記録に残る形式で交付しなければなりません。
なお、電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、一定の場合を除き、書面を交付しなければなりません。
また、取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引も対象であるため、発注事業者がフリーランスである場合にも義務が課されます。
■中小企業庁
ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_05.pdf


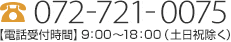
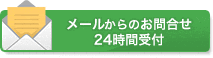

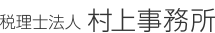 〒562-0003
〒562-0003