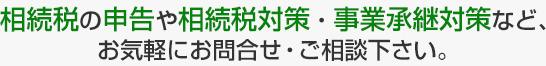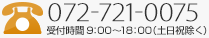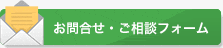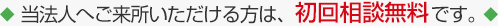2016年1月にマイナンバーカードの交付が開始され、2024年11月末の時点で、保有枚数率は全国で75%を超えている一方で、保有している人の携行率は46%となっており、定着するに至っていないのが実情のようです。
マイナンバーカードは、住民票の写しなどの公的な証明書の取得や確定申告、健康保険証、身分証明書として利用できます。
通常は、これらのサービスを利用するには、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードの持参が必要ですが、一部の行政サービスでは、マイナンバーカードの代わりに、スマホ用電子証明を利用することが可能になりました。
■総務省
マイナンバーカード交付状況について
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
スマホ用電子証明とは
スマホ用電子証明書とは、2023年年5月から開始したスマートフォン向けの公的個人認証サービスです。
スマートフォンへ電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩くことなくスマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用、申し込みが行えます。
先に書いた、低い携行率からも伺えるように、マイナンバーカードを自宅で貴重品として保管している人も、スマートフォンだけでマイナンバーのサービスを利用できるようになります。
スマホ用電子証明の気になる安全性ですが、機微な個人情報はスマートフォン内に記録されない、不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能等の対抗措置の実施など、暗号技術やさまざまなセキュリティ対策が施されているようです。
スマホ用電子証明書が利用可能なサービス
現在、スマホ用電子証明書が利用可能なサービスには下記のようなものがあります。
●子育て支援、引越しの手続き
●薬剤・健診情報、母子健康手帳の自己情報の閲覧
●銀行・証券の口座開設、携帯電話申込、キャッシュレス決済申し込みなど、民間のオンラインサービス
●住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書のコンビニ交付
また、今後開始される予定のサービスには次のようなものがあります。
●e-Taxの確定申告(2025年1月より)
●健康保険証
■デジタル庁
スマホ用電子証明書搭載サービス
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification
搭載方法
スマホ用電子証明書を搭載するには、マイナポータルアプリから申し込みます。
マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードの入力、マイナンバーカードの読み取り、スマホ用電子証明書のパスワードの設定等を行い申請します。
2024年12月6日時点で、スマホ用電子証明書を搭載できる対象端末は、Androidのみで約350端末となっており、2025年以降も端末の種類は増えていくようです。
また、今後リリース予定のiPhoneにもマイナンバーカード機能が実装されるとのことです。


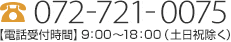
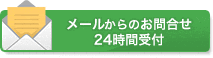


.jpg)
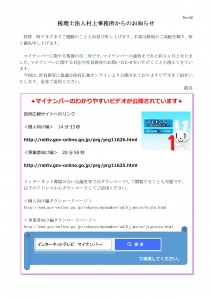

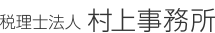 〒562-0003
〒562-0003