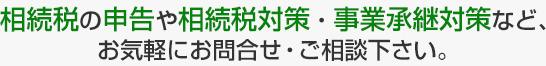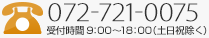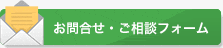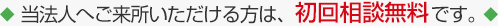新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、売上が減少している中小企業者等に対して、「固定資産税・都市計画税の減免措置」が設けられています。
原則として、申告期限までに必要書類を提出する必要がありますが、期限経過後の扱いとして宥恕規定も置かれています。
固定資産税・都市計画税の減免措置とは
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
【減免対象】
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
■事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
■事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
| 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
|---|---|
| 50%以上減少 | 全額 |
| 30%以上50%未満 | 1/2 |
【申告期限】
2021年1月31日までとされていますが、同日は日曜日に当たるため、翌日の2021年2月1日が申告期限となっています。
宥恕規定について
申告期限経過後の申告について、必要書類の提出先となる各自治体の市町村長が、「やむを得ない理由がある」と認めたときは、例外的に、期限経過後の提出であっても特例を適用することができるとしています。
「やむを得ない理由」とは、例えば
・必要書類の手続をしている人が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった
・新型コロナウイルス感染症の影響で会社が休業状態になってしまった
等のケースが想定されます。
ただし、このようなケースの認否については、各自治体の市町村長の判断に委ねられます。
大前提として、申告期限の遵守が基本であることを忘れずに、申告期限に間に合うように計画的に手続きを行いましょう。


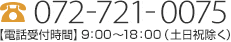
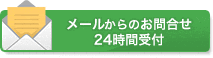

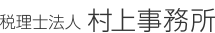 〒562-0003
〒562-0003