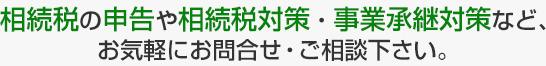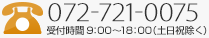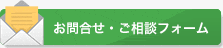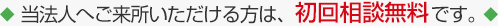豪雨や震災などの自然災害に対し、個人の支払った義援金が特定寄附金に該当すれば、寄附金控除の対象となります。
支払額は確定申告時に控除できますが、必要書類は義援金の支払先によって異なるので確認が必要です。
特定寄附金とは
国や地方公共団体、特定公益増進法人・財務大臣の指定を受けた公益社団法人等の団体に対して行った寄付金をいいます。
すべての寄付が控除対象ではなく、一定の寄付金に限られています。
■国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
義援金の支払先を確認
①災害対策本部等
被災した自治体に設置されることから国や地方公共団体に対する寄附金に該当します。
②団体等(日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など)
【注意点】
義援金を取りまとめる“受け皿”という位置付けの場合があり、最終的に義援金配分委員会(※)等へ送金されるのであれば,国や地方公共団体に対する寄附金①に該当します。
※義援金配分委員会等とは
災害の被災者を支援するために寄せられた義援金を、被災者に公平・平等に配分するための基準や方法を審議・決定する組織で、被災自治体や義援金受付団体、報道機関などから構成されています。送金先が義援金配分委員会等であるかどうかは団体等の募金趣意書等で確認できますが、確認できなければ団体等に直接確認する必要があります。
確定申告時に必要な書類
①災害対策本部等
・受領証
②団体等(日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など)
【専用口座がある場合】
・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料(募金要綱、募金趣意書、団体等HPの写しなど)
【専用口座がない場合】
・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料(募金要綱、募金趣意書、団体等HPの写しなど)
・預り証
ふるさと納税を利用した義援金寄付
ふるさと納税を利用して、特定寄附金に該当する義援金の寄付を行うこともできます。
その場合、支払先は自治体となりますので、必要書類は①に該当します。
ふるさと納税ワンストップ特例申請を行わずに、確定申告する場合、発行された受領書を大切に保管してください。
寄附金控除の証明書類の一覧表
| 支払先 | 申告に必要な書類 | |
|---|---|---|
| 災害対策本部等 | 受領書 | |
|
団体等 (日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など) |
専用口座あり |
・振込票の控え(又は郵便振替の半券) ・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料 |
| 専用口座なし |
・振込票の控え(又は郵便振替の半券) ・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料 ・預り証 |
|
|
ふるさと納税 ワンストップ特例申請なし |
受領書 | |


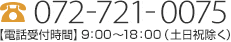
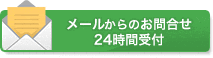


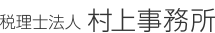 〒562-0003
〒562-0003