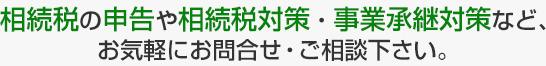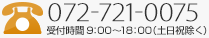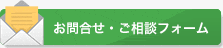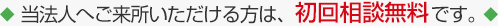民法改正により、本年9月1日から、紙の受取証書の請求に代えて、電子データ、いわゆる電子領収書の提供を請求することができるようになりました。
電子領収書の請求が可能になった背景
インターネット上での電子取引の増加や、ペーパーレス化の推奨、新型コロナの影響による在宅勤務の急増などにより、会社の経費精算で必要な領収書を電子データ(電子領収書)として交付してほしいというニーズがありました。
また、売手側も、新型コロナ感染拡大防止のため、非対面取引が増加する中で、領収書の印刷費や郵送費、交付のための設備や体制の整備等が過度な負担となる場面も出てきつつあるようです。
そこで、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、民法上これまでは、買手は領収書を書面でしか交付請求できませんでしたが、書面または電子領収書の交付のいずれかを選択して売手に請求できるようになりました。
対個人消費者との取引だけでなく、企業間取引も対象となります。
電子領収書のメリット
電子領収書が普及することで、様々なメリットがあると考えられます。
買手側のメリット
・環境保護への貢献
・財布が膨らむことによる煩わしさの低減
・紛失の回避
・新しい生活ツールとしての活用(各種アプリとの連携により、家計簿や、購入した食品のカロリーの自動計算等が可能)
・経費精算や確定申告への活用
売手側のメリット
・環境保護への貢献
・紙代や印紙代等の経費削減
・レジの混雑緩和
・キャンペーンサイトへの誘導等、販促ツールとしての活用
・購買データ分析によるマーケティングや販売戦略策定への活用
・消費者とのコミュニケーションツールとしての活用(紙レシートのように紙面の大きさの制約がなく、双方向のコミュニケーションが可能)
電子領収書の請求ができない例
電子領収書の交付を請求された売手は、それに応じる義務がありますが、体制や設備が整備されていない環境においては、スマートフォンやパソコン等を用いての発行が困難な場合も少なくないと考えられます。
そこで、「売手側に電子領収書を交付するためのシステム等が整備されていない場合」などは、売手に“不相当な負担”があるとして、買手は電子領収書の交付を請求できません。
電子領収書を電子インボイスとして交付等も可能に
令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まり、電子インボイスが導入されます。
電子領収書に売手の登録番号などインボイスの「記載事項」を記載していれば、売手は電子領収書を電子インボイスとして交付等することができ、買手はその電子領収書を保存することで仕入税額控除を適用できます。
■法務省:電子領収書の交付請求に係る「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A


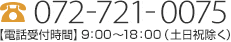
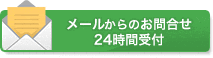

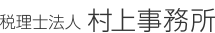 〒562-0003
〒562-0003