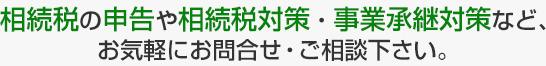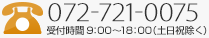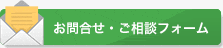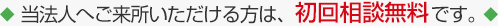福利厚生の一環として、従業員が自社株を定期的に購入・保有する「従業員持株制度」は、多くの企業で導入されています。
東京証券取引所に上場する企業のうち、およそ8割が持株会制度を導入しており、加入者も増加傾向にあります。
また、この制度を導入する企業の多くは、従業員持株会に加入する従業員に対して「奨励金」を支給しています。
ただし、この「奨励金」は給与として課税対象となるため注意が必要です。
従業員持株制度とは
従業員持株制度とは、企業が自社の株式を従業員に保有させる制度です。
福利厚生の一環として導入されることが多く、従業員が会社のオーナーシップを一部共有する形になります。
従業員があらかじめ申し込んだ金額を、給与や賞与から天引きの方法により拠出し、その拠出金をもとに自社株式を取得します。
【メリット】
■インセンティブの強化
従業員が自社株を持つことで、「会社の成長=自分の利益」となるため、業績向上に対するモチベーションが高まります。
■人材の定着
中長期的な資産形成が期待できるため、社員の離職率低下にもつながります。
従業員持株制度が福利厚生としても魅力があり、従業員満足度が向上します。
■経営の安定
長期的な安定株主としての従業員が存在することで、敵対的買収への防御や株価の下支えになる側面もあります。
【注意点】
株価が低迷すると従業員の士気低下のリスクがあります。
また、投資のため、一定のリスクも伴います。
企業側にとっては、制度継続運用のためのコストが必要になります。
従業員持株制度の奨励金とは
従業員持株制度における奨励金とは、従業員が自社株を購入する際に企業が一定額を上乗せして支給する金銭的支援のことで、制度への加入を促進するために、多くの企業で設けられています。
従業員が給料や賞与から天引きした一定額の拠出に対し、企業が数%~数十%を上乗せして株購入に充てるのが一般的です。
奨励金を設けることで、従業員持株制度への魅力が増し、加入率の向上が期待できます。
また、 長期的に見て従業員の資産形成にも貢献できます。
【例】
毎月の給与から1万円を拠出し、10%の比率で奨励金が支給された場合、拠出金1万円と奨励金1,000円を合わせた1万1,000円分の自社株式を取得できます。
従業員持株制度に係る奨励金は、会社から従業員に対して金銭で支給されるため、会計上、福利厚生費などの科目で費用計上している場合であっても、税務上は原則として「給与等」に該当します。
よって、毎月支給される奨励金であれば、毎月の給与に加算して源泉徴収されます。


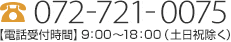
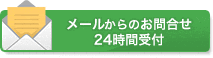

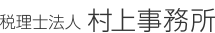 〒562-0003
〒562-0003