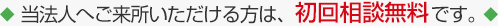働き方改革の一環で副業解禁が進む中、正式な所属先に籍を置いた状態で、所属部署以外の業務に携わる「社内副業」を導入している企業もあるのではないでしょうか。
社内副業を行った従業員に対して報酬を支払う場合、それが「事業所得」となるか、源泉徴収の必要がある「給与所得」となるかは、実態に基づいた判断が必要となってきます。
給与所得か事業所得なのか、判断基準となる判例
社内副業を導入する際に、本業(雇用契約)の所定労働時間とは別に、所属部署以外で業務を行えるよう、従業員と企業側で、社内副業についての業務委託契約を締結することがあります。
しかし、業務委託というその契約の名称から、社内副業は源泉徴収の必要のない「事業所得」であると即座に決定することはできません。
判断によく使われる判例は、昭和56年4月24日の最高裁での判決です。
給与所得か事業所得なのか、判断基準となる判例
上記の判決内容をわかり易くするために、営業部で働く従業員Aが業務委託契約を締結し、設計部で社内副業を行うケースで考えてみます。
■給与所得となる場合
副業先である設計部での業務について、企業側から従業員Aに対し、指揮命令や用具供与があるなど、設計部の他従業員と同じ状態で業務を行っている場合は給与所得となり、源泉徴収が必要です。
■事業所得となる場合
企業側からは、従業員Aに対しての指揮命令や用具供与などは行われず、従業員Aが成果物を納品した場合等は事業所得となります。
なお、従業員Aが、給与等を営業部のみから受給しており、設計部での社内副業の事業所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
社内副業のメリット・デメリット
通常は自身の所属する部署での業務が基本ですが、社内副業では他の部署での仕事に携わることができるので、経験の蓄積、スキルや知識の幅を広げることが可能となります。
企業側にとっても、人手不足や離職率低下の解消に役立つ面もあるでしょう。
一方、社内副業の課題として、従業員は本来の業務に加えて別の業務に取り組むため、スケジュール調整やマネジメントの複雑化などの負担増加が考えられます。
一部の大手企業で広がりつつある社内副業制度ですが、制度設計を工夫すれば企業規模を問わずに効果的に行える場合もあります。
その際は、源泉徴収の有無、業務量の調整、指揮命令系統の明確化などが留意点として挙げられます。


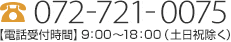
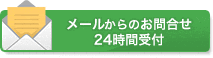

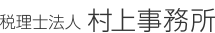 〒562-0003
〒562-0003