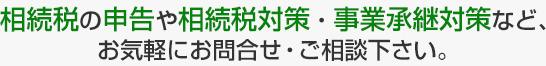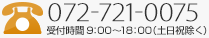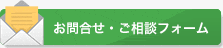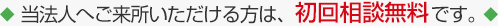ニュースでも取り上げられている、全国に増加する空き家問題。
老朽化した空き家の増加により、倒壊の危険や治安の悪化など、周辺地域に悪影響を及ぼすとして、社会問題となっています。
この問題を解決するために、空き家譲渡特例があります。
空き家譲渡特例とは
いわゆる空き家譲渡特例とは、被相続人が一人暮らしをしていた不動産(空き家や敷地)を譲渡価額1億円以下で売却した際の譲渡所得の金額から、最大3,000万円を控除できる特例です。
対象となるには、空き家を譲渡する際に、一定の耐震基準を満たす必要がある等、いくつかの要件があります。
空き家譲渡特例の対象となる譲渡資産の要件
①昭和56年5月31日以前に建築された建物である
倒壊の危険を解決するために、建物の耐震基準を満たすリフォームを行った後に譲渡するか、建物を壊して土地のみを譲渡しなければなりません。
②相続開始直前まで、被相続人が一人暮らしをしていた
被相続人に同居人がいなかった場合に限り対象となります。
③相続から譲渡までの間、ずっと空き家のままである
相続した後に、事業用に使用、または賃貸等の貸し付けに利用せず、譲渡するまでずっと空き家である必要があります。
その他の要件・詳細については下記URLでご確認ください。
■国税庁
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
老人ホーム入居等の特定事由について
被相続人が相続開始直前に家屋に住んでいなくても特例の対象となる場合があります。
・要介護認定等を受けて老人ホームや介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅等に入所した場合
・障害者支援区分の認定を受けて障害者支援施設等に入所した場合
なお、老人ホームなどの施設への入所ではなく、介護のために親族の家に住んでいた場合は、対象とはなりません。
また、被相続人が老人ホームなどの施設に入居している間の空き家については以下のような要件を満たす必要があります。
・相続開始直前まで被相続人の家財の保管等に使用されていた
・事業・貸付に使用されていない
・被相続人以外の者の居住の用に供されていない
申請時には、被相続人が要介護認定等を受けていたことを証明する書類や、老人ホーム等入所時の契約書、空き家の電気・水道・ガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類等が必要となります。


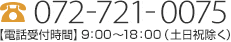
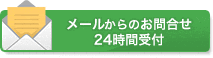
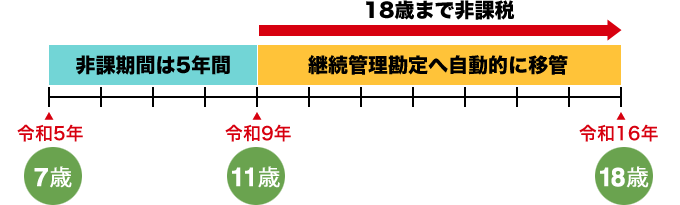

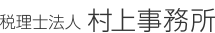 〒562-0003
〒562-0003