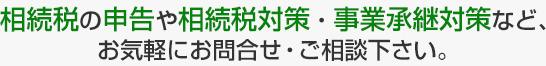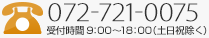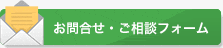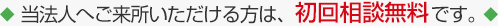年末年始、確定申告が近づいてくると医療費控除というワードを巷で耳にすることが増えてくる様な気がするのは、職業柄でしょうか。
前々回のブログでも少し取り上げていましたが、私もその医療費控除について少々お話しさせて頂きます。
サラリーマンでも出来る節税としてよく聞く医療費控除でありますが、この制度を利用するための前提として、2つポイントがあります。
それは、
① 確定申告を行うこと、
② 支払った証拠である領収書を保管しておくこと、です。
① 確定申告と聞くと難しそうに思えますが、大丈夫です。
源泉徴収票と医療費の領収書があれば出来てしまいます。
② 領収書の保管については、日々の生活の中で意識して保管するほかないと思いますので結果として控除が受けられなかったとしても年始から保管を始めておくことをお勧めします。
さて、必要な資料が手許にそろったら、医療費の領収書を集計してみましょう。
支払った医療費の金額が年間10万円
その年の所得金額(*1)が200万円未満の人はその所得金額の5%、
のいずれか少ない金額を超える部分が控除の対象(*2)となります。
(*1) その年の所得金額については源泉徴収票の給与所得控除後の金額をチェックしてみてください。
(*2) 控除額が最大で200万円というのも忘れてはいけないポイントでした。
例えば、年間18万円の医療費の支払があったとしましょう。
この場合、18万円▲10万円=8万円なので、8万円も税金が還ってくる!!というわけではありません。
実際に還ってくる金額は、8万円にその人の課税所得金額に応じて課される税率を乗じた金額となります。
計算してみて、「あ、なんだ、これだけか・・・」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
でも、確定申告で医療費控除を行えば住民税の負担も少なくなるというメリットもあります。
では、どんなものが医療費控除の対象となるか、どんなことに気をつけておきたいか、についても少しお話したいと思います。
医療費控除の対象となる範囲については、ほんの一例ですが以下のようなものがあります。
- 医師に支払った診療費、治療費
- 家庭用常備薬、風邪薬などの医薬品、市販薬
- 虫歯の治療、親知らずの抜歯、歯の矯正代・インプラント代(共に美容目的を除きます)
- 視力回復のためのレーシック手術、
- 通院のために使った公共交通機関の費用(いくらかかったか記録を残しておきましょう)
- 妊娠と診断されてからの健診検査・出産分娩のために要する費用など
また、以下のようなものは、よく勘違いしてしまいがちですが、医療費控除の対象となりませんので気をつけて下さい。
- インフルエンザなどの予防接種のための費用
- 異常が見つからなかった場合の健康診断の費用
- 入院に際し、自己都合で希望する差額ベッド代など
気をつけておきたいことについて、
一点目は、生命保険契約で受け取った入院給付金、健康保険から給付になった高額医療費等などはその目的となった医療費等から差引かねばならないこと(保険給付金等のほうが多い場合は他の医療費等から差引きません)。
二点目は、医療費控除の対象となるのは、自分の医療費だけではないということ。
税務上の扶養かどうかに限らず、生計を一にしていれば対象となります。
例えば、共働きの世帯では夫婦が税務上の扶養から外れていることもあると思いますが、その人が配偶者の医療費を負担していれば、その負担した金額は医療費控除の対象となります。
最後に最近の動向ですが、平成28年度税制改正大綱において、医療費控除の特例の創設が見込まれています(適用対象期間は平成29年1月1日~)。
この特例は、市販薬のうち一定のスイッチOTC医薬品を医療費控除の対象として一定の取扱により所得控除が受けられるといった内容になっています。
ただし、従来の医療費控除との選択適用となりますので注意が必要です。
(一定のスイッチOTC医薬品の購入の支払額▲保険金等により補填される額)▲12,000円=所得控除 ※限度額88,000円
一定のスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)、
簡単に言いますと、一旦、医者にしか使えない医療用医薬品として使われた後(安全が確認された後)、一般人でも買えるようになったものを言うようです。
具体例としましては、ロキソニンS、アレグラZなどがあるようです。
実際にこの制度が創設されるかは、国の最終的な決定を待ちましょう。
今回のお話が確定申告で医療費控除の制度を受けてみようという方々何かしらのお役に立てばと思います。
ありがとうございました。
税理士法人 村上事務所
檜垣寛明


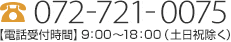
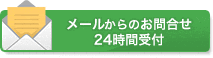



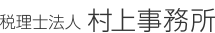 〒562-0003
〒562-0003