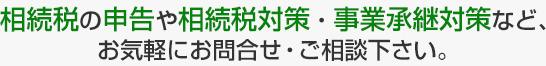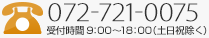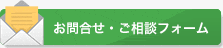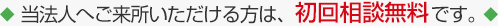繁忙期や人員不足等により、遅くまで残業をして、終電に乗れずにタクシーで帰宅することもあるのではないでしょうか。
この場合のタクシー代は、インボイス制度における「公共交通機関特例」や「出張旅費等特例」の対象とはなりません。
しかし、通常必要であると認められる通勤手当に該当すれば、一定の事項を帳簿記載することで、インボイスの保存は不要となります。
インボイス制度における公共交通機関特例・出張旅費等特例とは
■公共交通機関特例
従業員などが業務で使用する3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道等)に対する3万円未満の支払について、インボイスの交付義務が免除されるという特例です。
■出張旅費等特例
従業員等に支給する出張旅費(交通費、宿泊費、日当など)のうち、通常必要と認められる部分について、インボイス(領収書等)の保存なしに仕入税額控除が認められる特例です。
残業時のタクシー利用がそれぞれの特例の対象外となる理由
残業時のタクシー利用が上記特例の対象外となる理由には、以下のようなものが考えられます。
■タクシーは公共交通機関に含まれない
公共交通機関とは、 電車、バス、モノレール、フェリー、航空機など、不特定多数の人が定期的に利用できる交通機関とされています。
タクシーの場合、個別に利用されることが多く、運行が不特定多数に開かれている「定期運行」ではないため、公共交通機関とは異なる側面を持っています。
■通常勤務している場所からの帰宅は出張ではない
出張とは、業務のために通常勤務している場所から別の土地へ旅行することを指します。
よって、通常勤務している場所から自宅へ帰宅した場合は旅行といえず、一般的に「通勤」と整理されます。
通勤手当としての支給ならば、タクシー代のインボイス保存は不要
上記のように、残業時のタクシー利用は、公共交通機関特例・出張旅費等特例の対象外となりますが、「通勤手当」として支給するものであれば、一定の事項を帳簿記載することで、インボイスの保存は不要となります。
一方で、「交通費」として処理する場合、原則はインボイスを保存する必要があります。
■通勤手当と交通費の違い
| 通勤手当 | 交通費 | |
| 目的 | 自宅から職場までの通勤 | 業務遂行のための移動(出張や営業活動) |
|---|---|---|
| 会計上の扱い | 給与 | 事業主の経費 |
| 所得税 | 一定の範囲は非課税 | ー |
| 支給方法 | 現金・現物支給(定期券など) | 立て替え精算 |


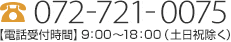
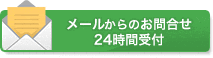

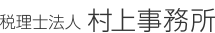 〒562-0003
〒562-0003