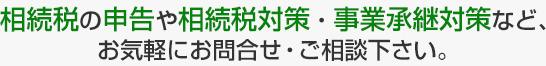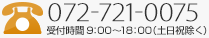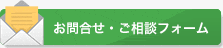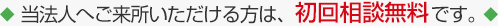空いた時間や隙間時間などの短時間で行える「スキマバイト」が、新しい働き方として注目を集めています。
人材不足を短期間で補えることから、アプリ経由でギグワーカー(スキマワーカー)を雇用している企業も増加しているようです。
短時間・短期的な仕事が多いイメージですが、賃金台帳に記載されているギグワーカーであれば、賃上げ促進税制における「国内雇用者」に該当するようです。
国内雇用者とは
企業や個人事業主に雇われており、国内の事業所で作成された賃金台帳に記載された労働者を指します。
役員は対象外となりますが、賃金台帳に記載されていれば、パートやアルバイト、日雇い労働者も国内雇用者となります。
■国内雇用者に含まれる範囲
・正社員
フルタイムで勤務し、安定した雇用契約を結んでいる人。
・契約社員・派遣社員
期限付きの契約で雇用されている人
・パート・アルバイト
短時間勤務や特定の条件で働く人
・日雇い労働者
日々雇用契約を結んで働く人
・外国人労働者
日本国内で合法的に働いている外国人(技能実習生、特定技能労働者など)
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、事業主が従業員の給与を前年度より一定以上引き上げた場合に、引き上げた額の一部を法人税から控除できる仕組みです。
企業が積極的に賃金引き上げを行うことを促進し、労働者の所得向上と経済の活性化を図ることを目的としています。
【賃上げ促進税制のメリット】
この制度の活用により、企業は税負担を軽減しつつ、従業員のモチベーション向上や人材確保も期待できます。
・企業の税負担軽減
賃上げを実施し、一定の条件を満たせば、法人税の控除を受けられるため、人件費のコスト増加を抑えることができます。
・従業員のモチベーション向上
従業員の所得が増えることで、生活水準だけでなく、仕事に対するモチベーションや生産性の向上にもつながります。
・企業のイメージアップをはかる
賃上げを行うことで、「従業員を大切にする企業」として企業イメージが向上し、人材の確保や、優秀な人材の流出防止も期待できます。
・経済全体への効果
給与が増加すれば消費が活発となり、経済全体の成長が促進されます。
賃金台帳への記載でギグワーカーも賃上げ促進税制の対象に
賃金台帳とは、事業主が労働者に対して支払う賃金の詳細を記録した帳簿のことです。
日本では労働基準法に基づき、すべての事業主に対して賃金台帳の作成・保存が義務付けられています。
労働者の賃金額やその賃金額の計算の基礎となる事項などが記載等されていれば基本的に、法定の様式は決まっていません。
ギグワーカーをスキマバイトのアプリ経由で雇用した場合、その情報はアプリの運営会社から企業側に対して、賃金額等の所定の事項が記載された明細書が発行されます。
その明細書の内容を、自社の賃金台帳に記載することで、そのギグワーカーは国内雇用者に該当するとのことです。


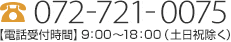
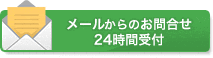

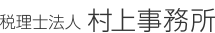 〒562-0003
〒562-0003