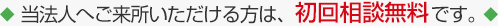相続税の改正ポイント:基礎控除額の引下げ
今回の改正で、特に影響が大きいものが、この基礎控除額の引下げとなります。
改正前であれば、「相続税なんて我が家には関係ない」と思っていたご家庭も、改正後は、申告義務者として対象の範囲になり得る可能性が出て参りました。
具体的には、以下のように改正されました。
【改正前】
5,000万円+(1,000万円✕法定相続人の数)
【改正後】
3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
基礎控除額が6割に縮小され、相続税の課税対象者が、改正前は日本の年間死亡者数の約4%のみの方だったものが約6%(1.5倍)に上昇すると見込まれています。
※改正内容は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産から適用されます。
参考:その他の改正内容
<相続税率の引き上げ、未成年者控除・障害者控除拡大、小規模宅地等の特例の拡大>
この基礎控除引下げに伴い、脚光を浴びているのが、生命保険を活用した非課税枠の利用です。また、生命保険は、早期の資金確保、遺留分の対象から外すことにも力を発揮します。
【非課税枠について】
被相続人の死亡によって取得した生命保険金等で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合、相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、以下の非課税限度額までは相続税の課税の対象となりません。
500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の方や相続放棄をした相続人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
つまり、例えば自分の死亡後に残された配偶者や子供さんのために定期預金などで積み立てていらっしゃる資産を生命保険に組み替えて、この生命保険金の非課税枠を使うことで、改正により基礎控除額を少し上回るようなご家庭であれば、基礎控除額内に納まることになります。
また、基礎控除額を大幅に超える財産をお持ちの方でも、中には、「高齢なので今から保険には入れないだろう。入ることが出来たとしても保険料が高く損するだろう。」ということで生命保険の加入を諦めて、せっかくの非課税枠を利用していない方も見受けられます。
しかし、そのようなことはありません。ある保険会社では90歳の方でも加入できる「一時払い終身保険」という商品があります。
1,000万円弱の保険料一括払い込みで、死亡保険金1,000万円を受け取れる商品です。利息はほぼ付きませんが、相続税の課税対象から除けるというのは大変メリットがあります。
さらに、生命保険には非課税枠以外のメリットが2点あります。
【早期の資金確保】
一つ目が死亡保険金の受取人をあらかじめ決めることができるため、早期に資金を確保できることです。相続人全員の合意が無ければ引き出せない預貯金とは違い、生命保険金は受取人に早期に保険金が支払われます。遺産分割前に発生する葬儀費用の支払いや、遺産分割が申告期限までに整わない場合の相続税の支払いなどにも備えることが可能となります。
【遺留分の対象外】
二つ目が原則的には死亡保険金は遺留分の対象外となることです。
原則として、死亡保険金は、遺産分割協議の対象外となります。
税務上は、実質的には相続財産であるとみなし、相続税の計算上、死亡保険金を含めて申告することになりますが、民法上は、受取人の固有財産となり、相続財産に含まれないという考えです。
財産を相続させたくない相続人がいる場合、生前に生命保険金に加入し、受取人を財産を相続させたい相続人とすることで、遺言書での遺留分の計算に生命保険金を含めないことが可能となります。
ただし、相続財産がほとんどなく、一方の相続人が高額な保険金を受け取っており、他方の相続人には、生命保険金を除いた相続財産の内の自身の法定相続分を相続させるというような場合には、相続人間で「極端に」不公平になるとして、この生命保険金が他方の相続人からの遺留分減殺請求の対象となる可能性がありますのでご留意ください。
税理士法人村上事務所では提携している保険代理店がございます。保険の専門家である代理店、税務の専門家である当法人がお客様にあった最善の保険活用を連携しご提案致します。ご興味のある方、相談をしたい方は、豊富な経験と実績のある箕面市の税理士法人村上事務所を是非ご活用下さい!!
税理士法人 村上事務所
代表社員・税理士 鶴田晃宗


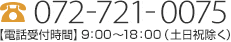
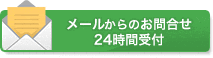

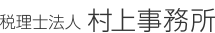 〒562-0003
〒562-0003