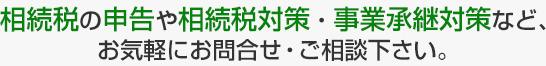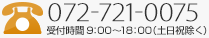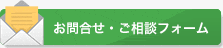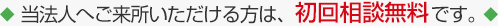新型コロナ対策でワクチン接種の担い手として産業医が注目されています。
常時50人以上の労働者を使用する企業は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっていますが、外部の医療機関に委託する場合と、個人開業医との雇用契約等の場合とでは源泉徴収の扱いが異なります。
産業医とは
産業医とは、企業等において労働者の健康管理等を行う医師のことです。
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を雇用することになった時から14日以内に産業医を1人以上選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
選任する産業医の人数は、常時雇用する従業員数などによって決まっています。
| 常用する従業員数など | 産業医の人数 |
|---|---|
| 常時使用する従業者数が50~999人 | 嘱託又は専属の1人以上の産業医 |
| 常時使用する従業者数が1000人以上 | 専属の1人以上の産業医 |
| 一定の有害業務に常時使用する従業者数が500人以上 | |
| 常時使用する従業者数が3000人以上 | 専属の2人以上の産業医 |
源泉徴収・消費税の取り扱いの違い
選任した産業医が、「個人経営の医師」か「法人・医療法人の勤務医」かによって変わってきます。
個人経営の医師
原則として、「給与」扱いで源泉徴収は必要、消費税不課税
産業医が個人経営の医師であれば、原則として給与収入となるので源泉徴収は必要で、消費税は不要(不課税)です。
企業等は、従業員と同じように源泉徴収票を年末に発行し、産業医自身で確定申告することになります。
法人・医療法人
「手数料」扱いで源泉徴収は不要、消費税課税
産業医の紹介会社等の法人、医療法人の勤務医であれば源泉徴収が不要で消費税は課税となります。
■国税庁:産業医の報酬
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。


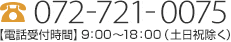
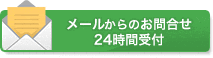

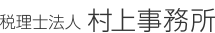 〒562-0003
〒562-0003