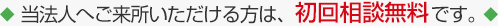令和6年度改正により、イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)が創設され、2月1日より経済産業省と一般社団法人ソフトウェア協会において申請受付が開始されました。
イノベーション拠点税制とは
イノベーションに関する国際競争が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、特許権・AI関連のプログラム等の知的財産からから生じる所得(ライセンス料・譲渡益)に対して、日本国内で支出した研究開発費の割合を乗じた額の30%に相当する金額を所得控除する制度です。
適用期間は、2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
対象となる知的財産は、青色申告法人が、2024年4月1日以後に取得・制作した、特許権やAI関連のプログラムの著作物が対象となります。
■経済産業省
イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_innovation_tax.html
ちなみに、2000年代から欧州各国で導入が開始され、最近ではインド・シンガポール・香港等のアジア諸国でも導入が検討されているようです。
イノベーション拠点税制のメリット
イノベーション拠点税制の本質は、日本で生み出した知財で利益を出す会社を税制で支援するというものです。
特に、AI関連技術を自社開発している会社や特許で収益を上げている会社には大きな利点があります。
以下に主なメリットを紹介します。
■法人税の負担軽減
対象となる特許やAIプログラムから得た利益の一部を、所得から差し引ける制度なため、その分、法人税が減ります。
■利益(成果)が出てから効く
研究開発は費用ベースですが、イノベーション拠点税制は利益(成果)ベースなので、成果が大きい会社ほど恩恵も大きくなります。
■知的財産の保有を戦略的に考えられる
特許やAIプログラムをどう管理するか、どこで開発するか、誰にライセンスするかなど、税務面からも戦略設計できます。
■日本に研究拠点を置くインセンティブになる
欧州では一般的である制度を、日本も同様に導入したことで、国際的な税制競争力アップが期待できます。
研究開発を日本で行うと有利なので、海外企業の日本進出の呼び水になる可能性もあります。
具体的にAI関連とは
「AI関連」と認められるには、官民データ活用推進基本法上の人工知能関連技術を活用したものを指します。
【例】
自社でAI技術を開発したプログラム→対象
他社のAIを使って画面だけ作った→対象外
また、AI関連であることを証明するためには、下記のように、一般社団法人ソフトウェア協会と経産省(経産大臣)の両方の確認・証明を受けることが必要となります。
この両方の証明書(コピー)を、法人税の申告時に添付します。
① 一般社団法人ソフトウェア協会の証明を取る
注意点:1件あたり5万円(税別)の審査料が必要になる予定
② その後、経済産業省の証明を取る
注意点:事業年度末日の「60日前~30日後」までにGビズFormで申請する


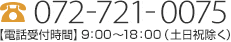
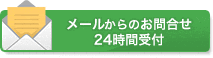

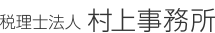 〒562-0003
〒562-0003