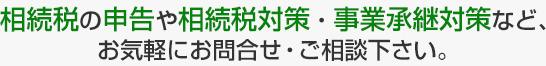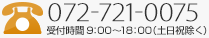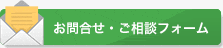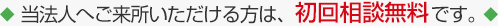インボイス登録をしたことで消費税を納めることになった個人事業主の方は、2025年(令和7年)分の申告でも「2割特例」というお得な計算ルールを使える可能性があります。
ただし、「2年前(令和5年)の課税売上高が1,000万円以下であること」が条件です。
この判定方法に注意が必要です。
混在する免税事業者の期間と課税事業者の期間
個人事業主が、令和7年分の消費税で「2割特例」を使うには、基準期間である令和5年の売上(課税売上高)が1,000万円以下であることが条件です。
ここで注意したいのが、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になった人の場合です。
この人は、令和5年の中で
・1月1日~9月30日:免税事業者だった期間
・10月1日~12月31日:課税事業者になった期間
という 2つの立場が混ざっています。
■免税期間の売上も「判定には含まれる」
免税事業者の期間中は、実際には消費税を納めません。
でも、「課税売上高がいくらあったか」を見るときは話が別です。
基準期間(令和5年)の課税売上高が1,000万円以下かどうかを判定するときは、
・免税事業者だった期間の課税売上高
・課税事業者になってからの課税売上高
この 両方を合計します。
つまり、この合計した結果が1,000万円以上になった場合、免税事業者だった期間があったとしても、と令和7年分で2割特例は適用できません。
課税事業者の期間(10月~12月):400万円(税抜)
この2つを合計すると、
700万円 + 400万円 = 1,100万円
となり、1,000万円を超えてしまいます。
この場合、令和7年分の消費税では2割特例は使えません。
そもそも2割特例とは
2割特例とは、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった人の負担を軽くするための制度です。
対 象 者: インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業主や法人
対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日
内 容:納める消費税を「課税売上高にかかる消費税の2割」とすることができる
適用条件:基準期間の課税売上高が1,000万円以下など
■国税庁
2割特例特設ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
なお、2割特例は2026年(令和8年)分で終了する予定ですが、個人事業者に対し、その後2年間「3割特例(課税売上高にかかる消費税の3割を納める)」という新しいルールが設けられる方針です。


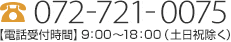
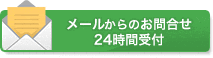

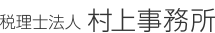 〒562-0003
〒562-0003