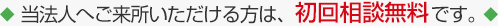11月下旬から急に寒くなりましたね。周りでも体調を崩す人が増えているような気がします。
さて先日、私どものお客様から次のようなご相談を受けました。前提として、
・ご本人は自営業だが多額の債務があり、全額を償還するのは事実上不可能。
・個人資産は無いが、推定相続人たる「子」が受取人となっている生命保険契約がある。
・私の妻は既に亡くなっており、推定相続人は「子」一人だけです。
・・という状況です
「自分が死んだら、子が債務を引き受けることとなるが、子が相続放棄をしたらどうなるのか?生命保険金は債権者に取られるのか?」
・・という内容でした。
ご存知の方もおられると思いますが、
・生命保険金は、「相続税法」上は一定額を超える金額について相続税の課税対象となる。
・しかし「民法」上の相続財産には該当しないため、生命保険金の受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受領することができる。そして故人の債務を負担する必要はない。
よって、上記の相談に対してはまず、
「子が相続放棄しても生命保険金は受け取れるし、そのお金を(本人の債権者に)取られる事もありませんよ。」
「でも、債務を控除できず、生命保険金の非課税規定(@500万)も使えないので、生命保険金が相続税の基礎控除を超えるならば、相続税の負担は生じますね。」
・・・が、とりあえずの回答となります。
ところがこれで問題は終わりません。民法では「相続人の順位」が定められており、この相談者の状況で「第一順位である子」が相続放棄をすると、「第二順位の相続人である直系尊属の内、故人に一番近い人:即ち親」が相続人となります。
つまり相談者の債務を親が相続することになってしまいます。
もしも親に十分な資産があったとしたら、債務を承継しても資金的には困らないかもしれません。ですが将来、その親の財産を相続する相続人(兄弟姉妹や相談者の子)からすると、相続する財産が減少する結果となります。
これはこれで困ります。
ですので今回の場合、親も相続放棄をするべきでしょう。
そして本件で親が相続放棄をすると、次の相続人は祖父母となります。
祖父母が既に没している場合、「第三順位たる兄弟姉妹」が相続人となります。
債務を承継する理由は当然無いので、兄弟姉妹も相続放棄をします。(兄弟姉妹が既に没している場合、その子供(=甥姪)が相続人となるので、甥姪も相続放棄します。)
ところで相続放棄の手続きは、原則として、
「<自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、>家庭裁判所に申述書を提出」・・・する必要があるのですが、本件では、
・子は、相談者の死亡を知った時から3ヶ月以内に、
・親は、子が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、
・兄弟姉妹(及び甥姪)は、親が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、
・・・それぞれ行うこととなりますのでご留意下さい。
**この様に相続放棄の検討は、「相続放棄が連鎖してゆく」事を念頭に置く必要がありますので慎重に行いましょう。
**今回のお話は、本来私ども税理士事務所が積極的に関与する案件ではないかもしれません。(手続は弁護士さんなどにお願いする事になるので)
ですがお客様が実際にこういった相談をまず持ち掛けるのは、私どもに対してです。
その場面で「ウチは税理士事務所なので税金しか分かりませ~ん」という事になってしまわない様に、「日々これ勉強なり」ですね。
今回は概略を説明できてホッとしました。
※気が付けばいつの間にか師走ですね.年内はあと2回更新予定です。ではまた。
文:税理士法人村上事務所 片山洋


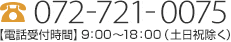
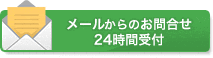

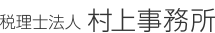 〒562-0003
〒562-0003